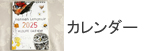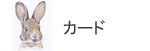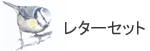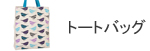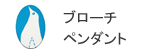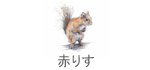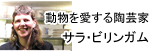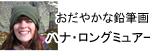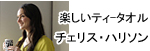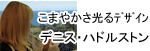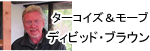英国のカントリーサイドめぐり
英国のカントリーサイドめぐり
イギリス最南端 ランズ・エンド、リザード・ポイント

イギリス南西部のコーンウォールに行った。
行く前、イギリスの地図を見て左端に突き出ている岬が気になった。ランズ・エンドという名前にも興味を引かれた。
「地の果て」と名付けられた岬は、旅人の心を捉えるために付けられたのかどうかは知らないが、この名前を見て行ってみたいと思った。
岬の先は海であると分かっていても行きたい衝動に駆られた。 コーンウォールに行くのは、今回で2回目だった。
初めて行ったときは、前日に友人宅に泊まり、行き先までの道順の確認やお勧めの場所などを教えてもらっていた。
ケンブリッジに住む友人にとってもコーンウォールは特別好きな地方らしく、お勧めの場所はいくつもあった。3日間の滞在ですべてを見て回わることはできないので厳選することにした。
私がガイドブックで行きたいと思った場所と友人が勧めてくれた場所を照らし合わせた。
私の方にはランズ・エンドが入っていたが、友人のリストには入っていなかった。いくつか候補地を決めていく中で私は、ランズ・エンドについて聞いてみた。
友人は、岬に行くのであれば、リザード・ポイントが良いと言った。ランズ・エンドは観光地になっているとだけ言い、リザード・ポイントの美しさについて語ってくれた。
名前とイメージだけで判断していた私は、友人の熱心な話しを聞き、ランズ・エンドは次の機会にするとし、リザード・ポイントに行くことにした。
リザード・ポイントは、イギリスの最南端にある岬である。「トカゲのしっぽ」という意味の名のとおり地図で見るとトカゲのクルッと巻いたしっぽの先のように見えなくもない。
ナショナル・トラストに管理されていて、岬の自然をそのままの姿で見ることができる場所だ。
ドラマティックな海岸の絶壁にはたくさんの野花が咲き、海鳥たちが強い海風に舞っている。絶壁沿いを散策することもできるので、スリリングなウォーキングを楽しめる。
リザード・ポイントの入り口付近で車を止め、近くにあったコーニッシュ・クリームのアイスクリームを食べてから岬に向かった。
空はカラッと晴れているが、風が強く、体を斜めに傾けながら歩いた。岬にはナショナル・トラストの小さな小屋があり、何人かその周りにいた。広大な海を見ると嬉しくなり気持ちが高ぶるのはいつものことであるが、やはり、丸く広がる水平線には感動した。
岬から横に続いている小高い丘に見える生き生きと茂る草花の新緑色が海と空の青の間でくっきりと写り、鮮やかだった。真っ青な海と絶壁にしがみつくように咲いている野花のピンク色のコントラストは、初めて見る自然美でありその美しさに感激のあまり涙を流しそうになるほどだった。
しばらく岬の周りにいた後、絶壁を散策するため3キロメートルほどのコースを歩いた。
リザード・ポイントに行ってから3年後に再びコーンウォールに行く機会があった。少し心残りもあったのだろう、ランズ・エンドに行った。
ランズ・エンドに近づくにつれ背の高い木々や建物はなくなり見通しが良くなっていった。膝ほどの背丈の草がびっしりと生える小高い丘が緩やかな起伏を成しており、それを幾度となく越えて行った。
周りに草以外に全く何もなく、平坦な場所に来ると砂漠の中を延々と続く1本道を走っているような感じさえした。この景色が続き、突然目の前に海が現れるかと期待した。
まるで草原と海がつながっているような景色が広がっているのではと想像し、もし、そうだとすれば「地の果て」にふさわしい景色ではないかと思い、とてもワクワクしていた。
しかし、見えてきたのは草原の中にはあまりにも不釣合いな白い大きな建物が、ぽつんと一つ。 友人が、観光地になっているとしか言わなかったのを思い出した。そして、この人工物が好きな人はほとんどいないだろうと思い、納得した。

荒野を歩く ダートムーア Dartmoor

地平線の彼方まで続くムーア。ヒースの生い茂る荒涼とした丘陵。初めて仲間たちと歩いて以来、その景色が強烈に私の心に残っており、忘れることができなかった。
もう一度あの景色を見たいと思い、ダートムーアに向かった。
1人でムーアを歩いた。途中に行き先を示す標識などなく、地図だけを頼りに目的地に向かう。どこまでも同じ景色が永遠と続いていた。その真ん中に立ち、どの方向に行くか、自分で決め、自らの足で進んで行った。
地図はあるが、この方向で正しいのか、時々不安になった。 しかし、目印となる建物も、看板も何もない。あるのは延々と広がる荒野の中に人が踏み固めてできた道だけ。
最初はどこまで行っても同じ景色が続いているように思えた。前に進めば進むほど不安に駆られ、何度も立ち止まりそうになった。つい先ほど見た景色が繰り返され、前に進んでいるかも分からなくなり、同じ所をぐるぐる回っているような感覚にさえなった。
来た道を戻ろうと思い出そうとするが、すべて同じ景色に見えて思い出すことができなかった。
自分と地図だけが頼りとなるこの空間が続く。正しいのか、間違っているのかもわからぬまま、ずっと歩き続けなければならない。
どれくらい歩いただろうか。遠くに荒い岩肌を見せる丘が盛り上がっているのが見えた。その頂辺に岩を積み上げてできた遺跡らしきものがある。あの岩の上に立って全景を見渡し、自分のいる場所がどこなのか確認すべく歩みを進めた。
遺跡は、前方に動かずにあるが、近づいているようでなかなか近づいてこない。雲行きが変わり、雨が降り始め視界が悪くなってきた。 疲れが出始め、道端にある石に腰を下ろす。
しかし、心細いのか、異様な孤独と不安に襲われ、落ち着いて休むことができない。足を止めてしまうと、次の一歩をどの方向に出していいのか分からなくなりそうに思えた。
地図を確認しただけで再び歩き出す。
自分がどこにいるのか、どこに向かっているのか、早く知りたかった。
ようやく遺跡の下まで来た。緩やかに頂辺まで続く真っ直ぐな坂道を登る。元気があれば間単に登れそうな坂が、疲れきった体には頂辺が遠く感じた。
1歩が重く、息を切らし、それでも上だけを見て進んだ。 頂辺に着いた頃にはさっきまで降っていた雨は止んでいたが、薄黒い雲に覆われてどんよりとしている。
目の前にある遺跡は、目的地へ続く通過点だと勝手に思い込んで登ってきたが、実際、正しい方向であるかどうかは分からなかった。
とにかく岩の塊によじ登り、立ち上がった。遺跡は、平らな岩を何層にも積み重なっており、7~8mの高さはあった。 頭上には、うっすらと灰色の雲が広がっている。
登ってきた方を見ると通り過ぎていった雨雲があり、雨を降らしている。その反対方向のずっと遠くに雲の切れ間があった。その切れ間から太陽の光が差し込み、空気中に漂う塵や水滴を照らし、淡い輝きとなって降り注いでいるのが見えた。

エクセター Exeter

イギリス南西部の町、エクセターへ観光で行った。
ロンドンから電車で約3時間。町の中心にはどっしりと構える大聖堂がある。大聖堂周辺には芝の広場があり、天気が良い日は多くの人が芝に寝そべったり、読書をしたりとくつろいでいる。
町のほとりを流れるエクセ川にはボートやヨットが停泊している。穏やかな気候のため1年を通してウォーター・スポーツを楽しめる。
エクセター郊外のに泊まった。今回のB&Bは、宿泊できるのが1日2組だけの黄色の壁の小さなコテージだった。
翌朝、もう一組の宿泊客である夫婦と朝食で一緒になった。一週間ほどかけて南西部をまわるホリデーに来ていた。
「Good morning」
あいさつして、天気の話しをした。
今日の天気は曇り。雨が降りそうなどんよりと厚い雲が窓から見える。
婦人は、そんな空模様を見て、
「今日は良い天気ね」と言った。
「どうして。曇りですよ」と聞くと、
婦人はイギリスの天気の気に入っている理由を話し始めた。
「以前にアメリカのカリフォルニアに行ったことがあるの。毎日、晴れだったわ。最初の数日は晴れの日が続いて良いところだと思ったの。でも、毎日、毎日、晴れ。何も変化のない天気が一週間も続くと飽きてしまったわ。イギリスの天気で晴れが続くことはほとんどない。
1日の内でも晴れたり雨が降ったりと変化に富んでいる。イギリスの天気は雨が多くて好きではないという人もいるけれど、私は、イギリスの天気が気に入っている。
晴れの日は、うれしいから天気予報を毎日チェックするの。あまり当てにならないけれどね」
私は、トーストにベーコンを挟んで食べていた。
婦人の旦那は、ベイクド・ビーンズを目玉焼き、ソーセージ、ベーコン、マッシュルームのすべてにかけて食べていた。
彼らは、明日までここに泊まり、今日はエクセターの町を中心に観光する予定を話してくれた。
私は、昨日、エクセターを観光していたので大聖堂のことやその前にあるティールームでランチにサーモン・オムレツを食べたことを話した。そして、今日は、電車でシェルボーンに行くつもりだと言った。
すると、婦人が駅までなら車に乗せていってあげますよ、と言ってくれた。私は、バスで行く予定だったので、婦人のお言葉に甘えさせてもらうことにした。
平日の朝ということもあり、町の中心に入ると混雑していたが、大きな渋滞もなくすんなりと駅まで送ってもらった。
ここまでは、よかった。私はお礼をして別れた後、いい人と一緒に泊まることができて良かったという気持ちで感謝していた。
夫婦の車を見送り、荷物を担ぎ上げた時に気付いた。
カメラを入れておいたバッグがない。
車の後部座席に座った私は、その足元にバッグを置いた。駅に着いたとき、駅まで送ってもらったことへのお礼を英語でどのように言うかを考えていたせいだろう。すっかりバッグのことを忘れていた。結局、「Thank you very much」と言ったくらいだったのに。
どうすることもできず、しばしその場に呆然と立っていた。
すると、道路を挟んだ向こう側の歩道をさっきの夫婦が歩いている。手を振り合図をした。夫婦もこっちに気付き、笑顔を返してくれた。 私は、夫婦に駆け寄り、バッグを車の中に忘れたことを伝えた。
夫婦は、驚いた様子だったが、車は駅の裏側の駐車場に止めてあるから取っておいで、と。旦那さんと一緒に取りに行き、無事、カメラは手元に戻ってきた。
さっき考えていて言えなかったお礼の言葉を言った。
婦人は、 「大袈裟ね。それより、大事なものを忘れるなんてどうかしているわ。今度は、あなた自身を電車に忘れないようにしなさいよ」と。
その後、旅行中に何度か些細なものを置き忘れすることがあった。その度に、婦人の言葉を思い出し、自分自身をどこかに置き忘れていないか振り返るのだった。

パブにて ウィンチェスター Winchester

ウィンチェスター大聖堂に行った時、ランチに入ったパブで、日本人に感謝しているおじさんに会った。
大聖堂の裏路地にあるアイビーが壁にびっしり茂っているパブ。外にもテーブルが6席ほどあり、2組のカップルがランチを食べていた。
中はいっぱいで外にしか席が残っていないかと思いつつドアを開けた。
パブの中にも空席はあった。
天気が良いので外で食べているのかと外を振り返った。外の席にも気を引かれたが、中にあったソファー風の椅子を見ると足はそっちのほうに向かっていた。
パブの中は、中央にカウンターがある。
それを挟んで両側に部屋が1つずつあった。たまたま私が入った側の部屋は人も少なく割りと静かだった。
もうひとつの部屋は、人がたくさん入っていて、立って飲んでいる人の姿も見える。トイレに行ったときに混んでいる理由が分かった。
トイレは、その部屋の奥にあった。
人をかき分け中に進んでいく。部屋の中央にあるテレビでサッカー中継が行われていた。チェルシー対サウサンプトン。ゴール前の攻防になると激が飛び交っていた。
みんなビールを片手に観戦している。
「あっ、もしかして」と思い、ランチが食べられるか不安になった。前に別のパブで夕食を注文した時、「サッカーの試合が行われているから食事は作れない」と断わられたことがあったからだった。気になってカウンターを見ると案の定ビールが飛ぶように売れていた。
席に戻り、メニューを見てチキン・サンドウィッチと紅茶を駄目もとで注文した。店員は、すんなり注文を受け付けてくれた。
食事を待っている間、おじさんが私の方をちらちらと見ている。そして、ときどき笑顔を見せている。見覚えのない人だったので、私に対してではないだろうと思い、横を見ると壁だった。
実は、パブに入った時からカウンターにいるおじさんの視線が気にはなっていた。ビールを片手にこっちを見ているなと思っていた。おじさんと目が合うたびに私も笑顔で返した。
変な人だと思いながらも。 「コミュニティーの場であるパブでは、知らない人同士でも、世間話で盛り上がり仲良くなる。そんな場所がイギリスにはあるのだ」と、イギリスのことを書いた本にあったのを思い出していた。
パブが混んでいる時、ビールなどを注文する際にカウンターで店員を待つことがある。そんな時、私と同じように順番待ちをしている人と話しをすることはよくあることだった。
自分たちのビールが来るまでの間、雑談をする。初めて会ったのに「調子はどうだい」と聞かれて、「いいよ」と言うと、「それは良いことだ、俺も応援しているサッカーチームが勝って調子がいいんだ」と、何気ない話をする。
でも、店員からビールが渡されると「See you」と言ってあっさり別れたものである。
エールがどんな味なのか知りたかったので店員に「苦味が強くなく飲みやすいのはどれですか」などと聞いていた時も、カウンターでビールを飲んでいたおじさんが店員の代わりにエールについて話し始めたこともあった。
そのパブに置かれていた3種類の味の違いを説明してくれた。話し終えるとおじさんは満足気にビールで喉を潤した。 「Cheers mate」 私は、エールについて教えてもらったお礼を言って立ち去った。
旅先で入ったパブでも気軽に会話が始まることは多々あったので、もし、よく行くパブであれば、そのような機会をきっかけに話しが合えば仲良くなるのだろうと思う。
でも、こっちを見ているおじさんは今までと違い、ちょっと不自然な感じがした。だけど、こんなこともあるのかと返す笑顔はひきつりぎみになっていた。
サンドウィッチを食べ終え、紅茶を飲んでいた。さっきまでちらちらと見ていたおじさんがこっちに向かって歩いてくる。紅茶を必死に飲みながら、話しかけるなよ、とオーラを出しているつもりだったが、その甲斐はなかった。
「隣に座ってもいいか」 紅茶をふき出しそうになるのをこらえながら、NOとも言えずにいた。
おじさんはビールの入ったパイントグラスを持ったまま私の前に座った。
ビールで頬が赤らみほろ酔い加減のおじさんは、あいさつをしてきた。 「何か用ですか」と聞こうと思ってやめた。でも、知らないおじさんに対して警戒している態度になっていたと思う。
おじさんはそんな私の様子には慣れている様子だった。
「日本人をよく見かけるよ。学生も多い。僕は、日本が好きなのだ。日本人に会うと話しかけるのだけど、シャイな人が多いね。でも、イギリス人もシャイな性格だからよく分かるよ」
おじさんが何を言いたいのか分からなかった。ただの酔っぱらいなら話しを聞くのはもうやめようかと思った。
サッカーの試合がハーフタイムに入ったらしく、向こう側の部屋から人がこっちに流れてきた。その中にいたおじさんの知人が、「サウサンプトンが0-1で負けているよ」とがっかりした顔で言って通り過ぎていった。おじさんは興味なさそうに生返事していた。
「僕は、サッカーは好きではない。イギリス人はおかしいよ。サッカーのことになると仕事もせずに観戦し、騒ぎ立てる。ビールを飲みながら、狂ったように応援をするなんてクレイジーとしか言いようがない」
おじさんのサッカー論は、私にとって関心のあることではなかった。
不快感がさらに募っていくのが、自分でも分かり早くこの場を立ち去ろう、本題があるなら早く話してほしいと思った。おじさんの話を黙って聞いていた。
すると、おじさんは話題を変え、別の話を始めた。
おじさんの話では、彼の母親は数十年前に日本に行き、今も日本で暮している。ただ、母親は行ったきり、一度もイギリスには帰って来てない。連絡も今はないのだそうだ。
「日本にどうして行ったのですか」 と尋ねると 「何のために行ったのか。日本のどこに行ったのか。はっきりとは覚えていないのだよ。」
話の意図がすぐに掴めなかった。紅茶を一口飲んだ。話を整理して聞く必要があった。おじさんの話は続く。
「数十年前に母は日本へ渡り、今も日本に住んでいることだけは確かなのだ。でも、何十年も連絡が途絶えているのは絶対におかしいと思う。僕は、何度も母に会うために日本に行こうとした。心配だからね。
だけど、僕はずっと前から心臓に持病を持っているため、飛行機に乗ることができない。残念でならなかった。治ったら行こうと思い、治療に専念していたのだが、この病は治りそうにないことが最近分かったのだよ。
この先、僕が日本に行くことはたぶんできないだろう。もしかしたら、死ぬまで母に会うことができないかもしれない。そう思うと辛かった。
それで、日本人を見るとお礼を言うことにしたのだよ。今では、日本人を見るとお礼を言いたくてしょうがなくなる。母をよろしく頼むという気持ちでね。
あなたがこのパブに入って来たときもすぐに日本人だと分かったよ。ずっと、いつお礼を言おうか、伺っていたのだよ。 日本のみなさんに母はお世話になっている。
本当は、僕が母の世話をしたいけど、情けないことに体が弱いからできない。日本のみなさんに頼むしかないのだよ。母が無事に暮しているならば、それはみなさんのおかげだと思うから、本当に感謝しているのだよ」
そう言っておじさんは、どこで日本人に教えてもらったのか、両手を合わせて何度も 「Thank you, Thank you」 を繰り返した。
パブを出る時、はずかしそうにあいさつするおじさんの息子夫婦と握手をした。まだ、サッカーの試合は続いているらしく、TV観戦している人たちのざわめきが聞こえている。おじさんは見送りに出てきてくれた。そして、握手を交わしたとき、笑顔でつぶやいた。
「Promise(約束)」 
英国で最も美しい村 カースル・クーム Castle Combe

「英国で最も美しい村と言われている、カッスル・クーム」。
全英一、最も古い街並みが保存されている村コンテストで何度も表彰されている村でもある。
3月のやわらかい日差しが気持ちのよい午後に訪れた。少し傾きかけたオレンジ色の陽の光が「はちみつ色」の家並みを照らしていた。
古い村を散策するのは、日本で言う京都や飛騨高山を歩く時と似ている。
小さな家の窓に飾られているポットの鉢には草花の緑が生き生きと茂っていた。4月には一斉に咲き始め、黄金色の石と美しいハーモニーを奏でるのだろう。
自宅の前庭を手入れしている人は、新しい花の苗を植え込んだり、家の壁に生い茂るバラのつるを剪定したりしている。そして、家の前を歩く旅行者に気付くたびに「Hello」と声をかけていた。
村の中心から少し外れたところに小川が流れている。そこに架かる橋の手前に小さな雑貨屋を見つけた。コッツウォルズの風景をスケッチした絵を探していたこともあり、入ることにした。
イメージしていた絵は、田園風景にフワフワと浮かぶ雲とコッツウォルズ丘陵のどこまでも続く牧草地、そして、草を食むヒツジ。
そんなコッツウォルズ地方に点在する村々へ車で向かう途中に見られる車窓からの風景を探していた。
壁に架かっている絵は、ほんの一部であり多くの絵は束になって壁に立てかけられていた。かなりの数の絵を1つ1つ見ていたので時間がどのくらい経ったのか覚えていないが、途中、気になる絵があるとじっくり眺めたりしていた。
私を含め2~3人の観光客がのんびりとお店の品々を見ていた。そこにウォーキングの帰り道に立ち寄ったらしき人が入ってきて、お店を一回りした後で興味深そうに私のほうを覗き込んできた。
彼は、朝からこの周辺をウォーキングしていたそうだ。ロンドンに住み、週末にコッツウォルズへよく遊びに来ているのだと話した。プライベート・ガーデンもたくさんあるし、家並みに心を癒される。
あと、ホームメイドの食事も魅力的だと、そんなことを話しながら彼は、私が素通りした絵を拾い上げた。その絵にはコッツウォルズの中にあるウィンチカムという村が描かれていた。
ウィンチカムのメイン通りが描かれているその絵を見て、彼はこの道沿いにあるこのティールームに行ったことがあると、それを指で示して言った。
「8年前に初めてそのティールームに行き、そこで食べたスコーンがとてもおいしかった。それとランチまでには売切れてしまうビスケットは、今までに食べたことがないほど最高の味だった。
あのスコーンとビスケットを食べるために毎年行っていたのだけれど、昨年、オーナーが変わってしまったんだ。イギリスではよくあることだけれど、もう二度とあの味を楽しむことができないと知った時は、本当にショックだった。」
私は、彼がコッツウォルズの他の村についても知っているのではないかと思い、今日行ってきた村の名前を言った。そして明日行く予定の2~3の村を挙げ、コッツウォルズに点在するたくさんの村の中でどこの村が一番気に入っているのか聞いてみた。
すると、少し困ったような顔をして、
「1日中ここにいても充分楽しめるよ。ウォーキングが好きならここに何日滞在してもいろいろなコースがあるから楽しめる。村そのものも良いし、さらに、村を取り囲む雰囲気がとても気に入っている。
朝、村を歩き始め、夕方には帰ってくる。ランチにここで買ったハムとチーズを挟んだサンドイッチを食べる。夕食にはレストランかパブで食事をする。そうすれば、カッスル・クームを満喫できるはずですよ。カッスル・クームが好きで来ているから、今のお気に入りはここだと思うよ。」
彼の話を聞いて、村だけを見ていたことをもったいなく思った。それと同時にコッツォルズの楽しみ方を教えてもらった気がした。急ぐことばかりに気を取られて、行ってしまったらおしまい、という旅行を続けていたのだろう。小さな村だから2時間くらいで見てまわれると思い、1日でたくさん見て回るようにスケジュールを立てってしまっていた。
時間の過ごし方でその人の価値観が分かるというが、そのことを実感した。絵を探すのを途中止めにして思わず店を出た。
どこを見て歩こうかと思ったが、ウォーキングをするとなると1時間くらい必要になるだろうと思い、あきらめるしかなかった。せめて村だけでも堪能できればと思い、村の中を歩き始めた。 歩きながら、自分なりに今まで訪れたコッツォルズへの印象を思い出してみた。
その時、絵を探すのに、気に入った村ではなく、そこに行くまでに見ている景色を探していたことに気付いた。私の中に印象として残っていたのは車の運転とその間に見た景色だったのかと思うと、ふとさびしくなった。
それから数ヶ月が過ぎ、パブで数人の仲間と飲んでいた時、イギリスに建築学の勉強に来ていた青年にコッツォルズについて聞かれた。
青年は、まだ一度も行ったことがなく、夏休みに入ったら行く予定だからおすすめのところがあれば教えて欲しいと知りたがっていた。
私は、あれからコッツォルズに行っていなかったので、その良さを身をもって体験していない。それで、いいたいことをどう伝えればいいだろか考えあぐねてしまった。
ガイドブックを片手に、すでに数十箇所のイギリスの建築物を見て回わったと豪語する青年は、私の沈黙を、もう忘れてしまったのだろうと判断したらしい。彼は、別に気にもとめずに、他に行ったことがある人に移っていった。
ウォーキング大好きなおじさん ストウ・オン・ザ・ウォールド Stow-on-the-Wold

ストウ・オン・ザ・ウォールドのユースに3日間泊まった。
立地は村の中心の広場にありとてもいい条件で、内装もリフォームしたばかりできれいだった。
夜の9時ごろ着き、パブの料理も終わっていたので(パブの料理は8時くらいで終わり、その後は飲み物だけになる所が多い)、共同キッチンで夕食を作ることにした。
共同キッチンではガスコンロや鍋などを他の宿泊客と共有するため、時間帯によって混んでいる事もあり、そんな時はお互いに譲り合って使う。
「何を作っているの」とか、 「今日はどこに行ってきたの」など
雑談をしながら料理をすることは、ユースではよくあることだった。
夜が遅かったこともあり、共同キッチンには誰もいなかった。広いキッチンを気兼ねなく使えると思い、のんびりと作り始めた。
10分くらいたった頃、一人のおじさんが料理を作りに入ってきた。
いろいろと話しかけてくるおじさんに最初は少し戸惑った。 おじさんは、ここのユースに今日から1週間泊まる予定で、ウォーキングを楽しみに来たそうだ。
今日は、最寄りの駅からここまでの6.4kmを歩いて来たそうで、途中、道に迷ってしまい、今さっき着いたのだといった。
昼過ぎに最寄り駅を出たらしいので、9時間近く歩き続けたことになる。
おじさんとは部屋が一緒だった。そのため、食事の後も話しは続いた。
明日から毎日、ウォーキングに出かけるのだそうだ。
翌日の夕食もおじさんと一緒になった。
ウォーキングのことを聞いてみると、なんだか落ち込んだ感じだった。
ウォーキングに出かけた先で唯一のジャンパーを失くしたそうだ。ウォーキングをしたというより、ジャンパー探しの一日だったそうだ。
食後、部屋でおじさんはカメラを見せてくれた。50年くらい前のカメラで、初めて見るカメラだった。手に取ってみると、とても重かった。
おじさんは、ウォーキングに行く時はこのカメラを持ち歩き、風景写真を撮っているのだそうだ。
風景写真は、曇り空の日が最もいい写真が撮れる。太陽の光が強い晴れの日より、曇り空のやわらかい光の中の方が、風景はきれいに撮ることができる。だから曇りの日が多いイギリスの天気は、風景写真を撮るには最高なのだと教えてくれた。
しかし、そのカメラに使われている電池が特別のものであるため、手に入れることが難しく、今は電池切れで撮影することができないのだそうだ。
3日目の夕食の時、おじさんは新しく買った紺色のジャンパーを見せてくれた。ウォーキングのついでに立ち寄った店で買ったのだった。とても気に入っているらしく、そのジャンパーを選ぶのにかなりの時間がかかったそうだ。
おじさんは、夕食にサーモンを焼いていた。サーモンはフタをしたステンレス製の鍋で焼かれていた。
焼き上がりの具合を見ようとおじさんがフタを開けた瞬間、サーモンが「パンパン」と音をたてながら鍋から飛び出してきた。
おじさんは、思わず 「bloody salmon」 と叫び、サケを追いかけていた。
おじさんは、毎年一週間、ストウ・オン・ザ・ウォールドにウォーキングを楽しみに来るのだそうだ。

ラウンドアバウト:信号のないロータリー状の交差点のこと。アストン Aston

初めての場所に行く時は、どんな街並みだろうか、おいしいものはあるだろうかなど、いろんなことを考えながらワクワクして行く。
陶芸家の工房には、レンタカーで行っていた。初めて行く街や村がほとんどで、迷うことなくたどり着くことはめったにない。1-2回同じ道を行ったり来たりするならまだしも、5-6回も同じ看板を見ると、つくづく方向音痴の自分が嫌になる。
その日は、オックスフォードから北にA40で20分ほどの所にあるウィットニーを抜け、A4095に出てノース・リースという村に行く予定だった。
オックスフォードの朝の渋滞を避けるため少し遅く出発したので、オックスフォード市街を出るまでは順調だった。
この辺りは、山もなく平坦で真っ直ぐな道が続き、道の両側に広がる牧草地を眺めながらの運転。レンタカーのフィアット車は独特のエンジン音を響かせ、BBC2のラジオ番組からはイギリスの流行曲が流れていた。
ウィットニーに行くまではよかった。町の中心にある13世紀に建てられた教会が迎えてくれた。町を抜け、目的地であるノース・リースを目指し牧場と牧場の間を突っ切って行った。30分くらいで着くはずがなかなかノース・リースの村が見えてこない。
地図で確認し、もう一度ウィットニーに戻ってやり直すことにした。なんと、これを4度も繰り返した。ウィットニーを抜ける時に必ず通る6差路のおかげである。
この6差路には、3つの連続した小さいラウンドアバウト(※1)があった。ラウンドアバウトに入る時には、どこで曲がるか決めていないと後ろから前から横から車の渦に巻き込まれてしまう。看板を見る余裕などなく、早くラウンドアバウトを抜け出すことだけに集中していた。
※1:ラウンドアバウトとは、信号のないロータリー上の交差点のこと。
右方車優先を原則とする。
ハンドルを右へ左へバタバタと回しラウンドアバウトをやっとの思いで抜けるが、少し行った所で看板を見て肩を落とす。この道でなかったことに気付いてユーターンを余儀なくされる。ラウンドアバウトが空いていないかと期待するもその思いは届かず、ラウンドアバウトの前に立ち止まるたびに車の量が増えているようにも思えた。
集中力が切れ、休憩することにした。。結局、6つある中の最後の一つのラウンドアバウトの入口を残してウィットニーに戻った。
スーパーマーケットのセインズベリーでオレンジジュースとハム&チーズのサンドウィッチを買って、近くの公園でランチとした。ランチの後、町を少し歩き、どんな場所か知るためにツーリスト・インフォメーションにも立ち寄った。町を手っ取り早く知るには、ツーリスト・インフォメーションは本当にありがたい。イギリス国内のほとんどの町や村にあり、係りの人もとても親切に教えてくれる。
何かあるかと思いながら、パンフレットの棚を眺めているとその中に“pottery(陶器)”の文字。
“Aston Pottery(アストン・ポッタリー)”。
地図を見ると、あの6差路のラウンドアバウトを抜けた先にあるお店だった。地図をもう一度確かめ、別のルートがないか探したが、かなりの遠回りになる。違う道に行って迷ってもつまらないことだと思った。
ノースリースに行った後でアストン・ポッタリーへ行くこととした。
このことをパブで友人に話したところ、友人は、ラウンドアバウトで間違った入口に入り、それに気付いたのが2時間ほど走った後だったそうだ。看板はところどころに出ていたのだが、地名を覚えていなかったため間違っていることに気付くのが遅くなったそうだ。
走り始めは見慣れない景色であってもそれほど気に留めることもなかったが、そろそろ見慣れた景色になってもいい頃だろうと思われるほど走ったにもかかわらず一向に目的地に近づいている気がしないので、地図を確認することにした。
友人は、現在地を確認しようと目の前の看板に書かれている地名を地図で探したが見当たらず、その時初めて自分が迷子になっていることに気付いた。自分が今どこにいるのか確かめるため、とにかく現在地を地図で探した。
友人は、現在地を見つけて驚いたそうだ。まったく逆の方向に行っていたのだ。友人の不幸はさらに続く、急いでユーターンして来た道を戻っていたのだが、迷子になったことに動揺していたのかスピードの出しすぎで、事故を起こしそうになった。さらに、事故すれすれの運転でさらに心臓の鼓動が激しくなっていた。一瞬、まぶしい光が友人の目を刺した。スピードカメラのフラッシュ光だった。
初めての場所に訪れる時、ガイドブックを見ながら、ここに行ってみたい、あれも見たい、地元の料理はおいしいかなとワクワクしながら行く。
ただし、道に迷わなかったらのことである。
ウィットニーについて
ウィットニーは、コッツウォルズの入口にあたる町です。
1669年以来、毛布作りで有名となった町です。毛布は、原料にコッツウォルズの羊毛と地元の綿毛を使って作っており、世界的にも高品質なものとして知られています。エリザベス女王もここで作られた毛布を使用しているそうです。
ウェールズのブレコン・ビーコン国立公園にて Brecon Beacon

遥か遠くにブラックマウンテンが見えている。
やっとブレコンの山頂に立つことができた。
視界を遮るものがなくかなり遠くまで見渡せる。
眼下には霞に包まれたブレコンの町が見えている。
一緒に登ったフィルは、一眼レフカメラを取り出しシャッターを切り続けている。
他の仲間たちもその景色に感動して、雄叫びを上げている人もいる。
女の子の中には、高所恐怖症の人もいて景色を一目見て卒倒してしまい、頂上の真ん中で泣きながら地面にしがみついている。
標高800m強のブレコンの山は、日本の北アルプスのように鋭い剣先のように聳え立つ山ではなく、なだらかな曲線を大きく描いたような丘陵だった。
その丘陵は、麓から20mも登ると背の高い木はなくなり、ヒースや草のみとなる。
ブレコン・ビーコンズ国立公園内にあるPen-Y-Fanという山。この辺りは、ムーアと同じような景色が広がっている。ムーアは、土質が乾いた砂であったり、酸性土壌であったりするためヒースやゴースなど生息できる植物が限られてしまう。
それらの背の低い植物が何キロにも渡って這うように茂っている。そこは、不毛の土地であり「荒野」と表すのが適当だと思った。
ウォーキングの仲間たちと一緒に登った。山の麓から頂上までほぼ一直線の登山道を歩く。登山に慣れていない人もいてペースはゆっくりだった。30分ごとに休憩を取り水筒に入れておいた紅茶を飲み、一息入れては登るというのを繰り返し、頂上を目指した。
途中、この近辺に住むおじさんが登山道を修復していた。おじさんは、登山道の砂が落ちていくのを防ぐために約2m間隔で石を埋め込んでいた。
「乾いた赤土が、足跡の数だけザザァーと落ちていくのだよ。風が吹くと目を開けられないほど砂が舞い、砂は下へ下へと向かっていく。さらに、雨が降ると多量の砂が押し流されていく。
登山道以外は、草が地中に根を張っているのでそれほど風化が激しくないが、登山道は、ひどいものだよ。だから、このように登山道に対して垂直に石を埋め込み、落ちてくる砂を堰き止めている。登山道が整備されていないと登山道の風化がその周りにまで及び、植物たちの根を掘り起こし枯らしてしまう恐れがあるからだよ。
では、なぜここに生えているヒースや草などを守るのかというと、それには意味がある。
ヒースなどは、小さな動物の棲み処になっていてここには約5,000種類もの生物が棲んでいると言われている。場所によっては、鳥が巣を作っているところもある。もちろん、ヒースなどのようにこの土地でしか見られない特有の植物を守っていくのは当然のことだろう」
おじさんは、1人でその作業をしていた。でも、登山者がここを通るたびに立ち止まり、話しかけるのでさびしくはないが、ぜんぜん作業がはかどらないのだと言って笑った。
おじさんと別れ、仲間たちと頂上に向かう。頂上が近づくにつれ、風が強くなってきた。3時間かけて頂上にたどり着いたとき、ピークに達していた疲れは吹き飛んだのだった。
風はさらに強さを増しているが、仲間たちの顔からは笑顔がこぼれていた。
男たちは、もう一歩足を出すと下に落ちてしまいそうな頂上の端に立ち、腰に手を当て、物思いにふけた表情をして遠くを眺めている。
女たちは、座れそうな場所を見つけてみんなで輪になって座り、紅茶やビスケットを食べておしゃべりをしていた。
記念写真を撮って下山した。
下山の途中、ブレコンの裾野に沈む真ん丸い太陽が見渡す限りの大地を夕焼け色に染めた。 
ムーアに囲まれた小さな町 アルストン Alston

どこまでも続く広大なムーアの丘を越え、アルストンの町に着いた。初冬のムーアには、どんよりと黒く厚い雲がたれ込めていた。いつものムーアよりもさらに神秘的な力があふれているように感じ、身震いした。
行き交う車もなく、標識もない。ムーアの中を通る1本道を走り続けた。いくつも続く山道に特有のカーブをぎこちないハンドルさばきでやり過ごしていく。こんな時に限って、ガソリンの残量を示すゲージが「Empty」を指し、心細さに拍車をかけた。
アルストンの町は、カンブリア地方で活躍するクラフトマンのガイドブックで知った。そのガイドブックに載っていた陶器の写真に魅かれてやって来た。
イングランド北部の小さな町であるアルストンは、ムーアに囲まれた谷間にあった。
町に着き、陶器の情報を集めるためツーリスト・インフォメーションに行った。案内係のおばさんは、地図をコピーしてくれたり、電話で確認してくれたりと懇切丁寧にしてくれた。人のあたたかさに触れ、さっきまでの心細さが消え、落ち着きを取り戻しつつあった。
マクロ夫妻が作陶活動しているストコエ・ハウスは、町の中心にある17世紀に建てられた由緒ある家であった。
妻のシルは、ムーアの景色をモチーフにした壁掛け、花瓶、お皿を作っている。ムーア独特の色合いを土そのものに色付けし、1色ずつ焼く。そして焼き上がった土を何層にも貼り合わせ作り上げていた。
夫であるレイの代表作は、陶器のランプ台だった。円柱の中心をくり貫き、空洞になっているところにランプをセットすると、葉の間からやわらかい光がこぼれるように部屋を照らしていた。風に揺れている木のデザインものや緑豊かなオークの木をイメージしたものなどいろいろあった。
マクロ夫妻のどちらの陶器か聞かなかったが、淡い緑色の木が彫られたアロマテラピーの台が気に入った。アロマ液をろうそくの火で下から焚く形のもので、木の葉の部分がくり貫かれており、ろうそくの光が木に差し込むこもれびのように見えた。ゆらゆらと揺れる火の光が照らす空間は、とても居心地が良かった。しばらく、木の葉の間から見えるろうそくの炎を見つめていた。
ムーアに囲まれた小さな町で、陶器とろうそくの光に元気をもらった。帰り道のムーアが、どのように見えても身震いは起きないような気がした。
アルストンについて
アルストンムーアに囲まれた谷間にある町です。蒸気機関車の発着地があり、北カンブリアの美しい渓谷を見ることができます。