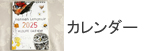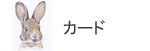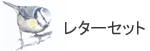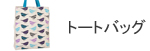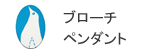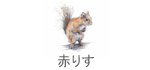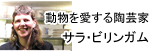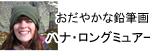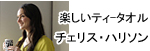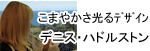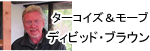英国のカントリーサイドめぐり
イギリスのナショナルトラストのガーデンで会ったエリスとポール

ナショナル・トラストの職員であるエリスには、イングランド北部のキャンプでお世話になった。
エリスは、参加者のお世話や仕事の内容を説明するボランティアコーディネーターだった。
エリスは、仕事をする前にその目的をみんなに伝え、手本を見せる。そして、みんなと一緒に作業をする。分からないことがあれば、みんなはエリスに聞いていた。
1人1人と話す時の表情は、とてもおだやかであり安心感を与えてくれた。
そして、エリスのそばにはいつもポールがいた。
エリスの夫であるポールはキャンプにリーダーとして参加していた。
ポールはナショナル・トラストの専属ガーデナーだった。
好きなサッカーチームは、出身地であるリバプールであり、気さくでまじめな人だった。
キャンプに参加している人たちは、同じ宿舎で寝泊りする。
ポールは、今回のキャンプの参加者にリーダーがいなかったので特例として参加していた。だから、みんなとは一緒に泊まることはなかったが、毎朝、約束の時間の10分前にはやって来ていた。そして、みんなを乗せるミニバスの点検をしたり、掃除をしたりした。
貴族の屋敷にあるガーデンで作業をした時のことだ。
午後の作業を終え、日が暮れるまでまだ時間があった。みんなで屋敷の中を見ることにした。ポールは、何度も見たことがあるのでここで休んでいるよと言って一緒には来なかった。みんなと一緒に
「やっと終わったね」
「今日も疲れたね」
とおしゃべりをしながら屋敷に展示してある当時のままの品々を見てまわった。 3階の部屋に入り、窓から外を眺めた
。さっきまで作業をしていたガーデンが見える。彼はその前にまだいた。腕を組んでベンチに座っている。手を振ってみるが、こっちには気付いていない。誰かが、
「彼は、おそらく作業を始めるよ。コンポスト作りがまだ残っていたからね」
と言った。 みんなは、ポールがどうするか、開かない窓に顔を近づけて覗き込んだ。ポールの動きを全員で見守った。ポールが顔を横に振れば、
「何か探している様子だぞ」
と誰かが口に出して言った。 ポールが思い立ったように立ち上がった。
「どうする?」
コンポストのほうに行くか、別のほうに行くか、賭けでもしているような感じだった。
ポールがコンポストに向かって歩き出し、スコップを持つとそれをかき混ぜ始めた。
「やっぱりそうだったか」
みんな、ホッとした。ポールはせっせとコンポストを混ぜては、ガーデンに運んだ。
ポールには頑固なところもあった。
作業が休みの日に1800年代に建てられた歴史的建造物を見学に行った。ランチまでは一緒にとったのだが、建造物を見に行かないと言う。
一度言ったら絶対に考えを曲げないのはイングランド北部の男の気質なのだろうか。みんなで何度も誘ったのだが、前に行ったことがあるからと断られた。
ポールは、車の中で約2時間をたった1人で待っていた。
一緒に行動したほうが時間が過ぎるのも早いし、楽しいと思うのだが、運転席に座り、ただひたすら待っていた。
ポールと一緒にパブに行く機会があった。いつもはゆっくりと座って話をすることもなかったので楽しみだった。
ポールは、ベジタリアンのメニューにあった野菜サラダ、ベイクド・ビーンズをパイ生地で包んだもの、パン、アイスクリームのセットを食べ、ビールは飲んでいなかった。
ポールは、陽気に話している。
パブという場所がそうさせるのか、みんなも上機嫌で楽しそうである。
ポールは、自分がベジタリアンになったのはエリスとの出会いがきっかけだったと話しはじめた。エリスが20代のころにインドへ旅に行ったこと。エリスは、そのころから自然保護に関心があったが、どのように関わっていくのがよいか悩んでいたこと。
インドで、誰に出会い、何を見たのかは具体的には聞いていないが、インドの食文化に菜食主義があることを知り、その主義の中に自然保護に通ずるものを見出したこと。
そして、エリスは彼女自身でできる自然保護活動の1つとして、自らの食生活をベジタリアンにしたこと。
ポールは、エリスに出会い、一緒に暮らしていくためにベジタリアンの食事に変えた。そのときは、エリスがベジタリアンとなった理由は、ポールにとってどうでもいいことであり、それよりも、一緒にいたいという思いのほうが大切だったそうだ。
「ベジタリアンのアイスクリームはおいしいの」
そのアイスクリームは、材料に乳製品の代わりに豆乳を使っているものだった。
「美味しいよ。本当に。試してみるか」
ポールはそう言ってスプーンを差し出した。
キャンプの最終日。その日は、ハローウィンということもあり、いつもはキャンプの仲間たちだけだった夕食に2人を誘うことになった。エリスは、大きな鍋いっぱいにマッシュ・ポテトを作ってきた。まだ、食事の準備中だったのでみんなとキャンプの感想や明日の予定などを話していた。
私も明日から湖水地方に行く予定を話していた。エリスは、それを聞き湖水地方はどこに行ってもナショナル・トラストの看板があるから見るところがたくさんあるよと教えてくれた。
私が車で行くと言うと、行き方を教えるから地図を見せてと言った。しかし、準備の悪い私は地図を持っていなかった。すると、ポールが車に載せてあった自分の地図を持ち出してきてくれた。
エリスがその地図を受け取り、ここからの道順を地図に書き込んでいった。そしてこれで大丈夫と言って私に地図を渡した。私は、マークされた道路の番号と道順をノートに書き写し、地図をポールに返そうとした。それを遮るようにエリスがその地図を受け取り、私に返した。
「私たちは、明日、遠くには行かないから地図はいらないの。この辺りの地理は分かっているから大丈夫よ。だけど、あなたは遠くに行くでしょう。地図は持って行っていいですよ」
そう言って、エリスはポールのほうをチラッと見た。ポールは、地図を私から受け取るつもりで出しかけていた手をそっと引き、微笑んでいた。
ハローウィンの夕食の準備が整い、かぼちゃを囲んで始まった。フライド・ポテト、ソーセージ、ハンバーガー、マッシュ・ポテトなど簡単な料理がテーブルに並んだ。
食事の後は、マークス&スペンサーで買ったケーキを食べ、それぞれ紅茶やビールを飲んでくつろいだ。
ゲームをしたり、おしゃべりをしたりして盛り上がっていた。その時、どこから入ってきたのか一匹の蝶が飛んできた。
動きを止め、みんなで蝶を見上げ、どこに飛んで行くのか見ていた。
鮮やかなオレンジ色の羽をひらひらさせながら一度天井まで上がり、くるくると回りながら降りてきた。みんなが見つめる中、ゆっくりゆっくりとエリスの頭の上に降り立った。
「美しいアクセサリーでしょう」
うれしそうに微笑み、じっとしていた。蝶は羽を休め終えると再びどこかにゆらゆらと飛んでいった。
次の日、エリスはレンタカーのオフィスまでついて来てくれ、車を借りる手続きを一緒にしてくれた。ポールは、車の中で待っていた。
イギリス北部の英語は訛りがあり、聞き取りづらかったが、エリスがいてくれたおかげで助かった。エリスが分かりやすい英語に言い換えてくれたからである。おかげで契約書にサインするまでスムーズだった。
ところが、キーを渡され、緊急連絡先を聞かれた時に困った。日本の連絡先しかなかったため、それを言うことは不適切だと思いうつむくしかなかったが、
「緊急連絡先はここ」
と、エリスが自分の電話番号を差し出してくれた。
車を無事に借りることができ、私の車が置いてあるところに向かって歩いていたとき、ポールがこっちに歩いてきていた。あまりにも時間がかかっているので様子を見に来たのだった。
エリスは、ポールに気付くと、手続きが今さっき終わったことをいった。そして、私の緊急連絡先を自分たちの電話番号にしたことも伝えた。ポールは、それはよかったと何度もうなずいていた。
エリスとポールにもらったA3よりひとまわり小さい地図は、旅の途中で雨に打たれてしまった。そのため、今は半分から上の部分がしわしわに波打っている。ところどころ印刷がはがれて見えないところもある。だけど、イギリスへ旅に行く時にはいつもその地図を持ち歩いている。